
詩堂アタル
「サビに使えそうな進行はあったけどAメロやBメロはどうしよう…」みたいな。
-Contents-
0.読み進めやすくするために
- 音楽における「キー」が何のことか分かる
- ダイアトニックコード等、大まかなコード理論は知ってる
- ※音楽理論の参考書等も買って持っている

詩堂アタル
とはいえ知らないところを読み飛ばしていっても問題ない記事にはなってるかと。
(※後で理論を学んで引き出しを増やしていこう)
便利なもの。
コードの音内容を鍵盤表記で載せてるコード進行参考書等がパッと見で分かりやすくて便利かと思います。
詩堂アタル
ボクはDTMのピアノロールを活用してます。ノートを並べて比べられるのが直感的。
この記事で書いていくこと。
あくまで網羅ではなく、考え方の整理になる話。 たとえば「今何をすれば良いか分からない、何を調べれば良いか分からない…」から進展するかもと思われる話+コード進行の組み立てに役立つ発想的なのの紹介とか。 重要なのは理論の名詞ではないというのも心に置いておきたいところ。
詩堂アタル
「理論ではこう書かれてるから」ではなく、「何のために自分はそうしたいのか」が大切。
推奨したいこと!
自分なりのメモ帳を用意してネタ帳を作っておくと便利かと。 好きなスケールの雰囲気等 印象のメモまとめだったり、コード種類だったり、ダイアトニックコードなどなど。
自分の好きだと思ったものを集めておくと、あとで何かしら進行を組み立てたいときにそこから始めることが出来ます。
1.「2タイプ」あるコード進行。
- コードも歌う曲
- メロディだけが歌う曲
コードも歌うタイプ
コードを空気感と捉えるなら、まさにその世界観における雰囲気。そんなコードが歌うように凝っていると、言葉のように直接的な雰囲気が表現として宿ります。
怖い映画とかでの「怖いシーン」には後ろで「怖い音楽」が流れますよね。ボクの知る限りHIP HOPとか流れてないはず。某 貞〇のアンサーとかいらない…。
そういった場面での音楽は まるで感情の代弁。登場人物が「怖い」と言わずとも 視聴側にまで伝わる感覚。
曲中においての俳優がメロディなら、このコード進行タイプは その 代弁的BGM と たとえられるでしょう。
メロディに任せてるシンプル進行タイプ
この場合のコード進行はシンプル。感情の代弁というよりは、場所感。 どんな場所で 何を(メロディで)歌い上げているかみたいな曲になる。2.メロディのように決める方法
ここ「メロディの作り方記事」でも少し触れました。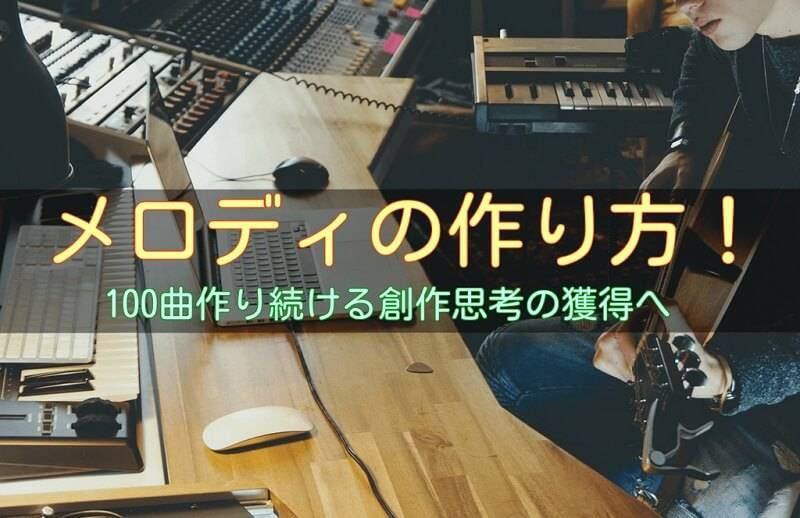
「作れない」卒業!メロディの作り方のたった2つのコツ
...
※ちなみに上記1.内での「コードも歌う」は積極的にコードが動くことのたとえ。
この2.内での「歌えるルートライン」というのは違和感のない音程進行感としての自然さをたとえています。
【参考になる動画】
(3:29秒くらいから特に!)
コード進行を組み立てるのにも利用できる お話。
ルートで作った進行をコード(和音)にするには?
基本は3度と5度を足すこと。キー(メジャーかマイナーか)からダイアトニックコードを確認しておけば比較できて よりスムーズに組み立てられるかと。 組んだルートの内容によっては複雑な場面(ルートがノンダイアトニック(以降 Nd)等)も出てくるかと思いますが、その場合は前後のコードが分かれば解決です。 そのコード間に違和感なく入れるルートなら、その前後のコードから絞り込めます。
たとえば半音進行であれば経過和音かクリシェのどちらか。
それ以外の場合は前後のコードから、平行調や同主調、他 本来向かうはずのダイアトニック内での進行先を探り「そのNd音をテンションに使えるコード」で探せます。
その展開系と言えるかと。
コード名で悩んだら。共通音と展開。
本来理論の上では正確な表記が求められるのでしょうが、メロディに使われてる音とコードの内容から どうとでも取れそうな場合は 分かればOK(笑)ってことで。 「前後のコード名の流れ的に こう表記すれば良いか」くらいで良いかと。(笑)
詩堂アタル
C6/Aと書くのかAmと書くのかは前後のコードの名前次第的な。
3.ダイアトニックコードについて簡単に。
確認として、たとえばキーがCの場合。
C Dm Em F G Am Bm(-5)
のことですね。(-5は ♭5とも書く)
ディグリーネームで書くとこうなります。
I IIm IIIm IV V VIm VIIm(-5)
本記事内では 主に こっち、ディグリーの方で進めていきます。
各コード間の機能関係 確認。(進める進行先)
I~VII内で、それぞれのコードの向かえるコード先。 【基本として】トニック(T)とサブドミナント(SD)、ドミナント(D)の関係。- T(I)…元であり終止でもある。SDにもDにも進める。
- SD(IV)…緊張させる。TにもDにも向かえる。
- D(V)…ダイアトニック内で一番緊張させることが出来る。Tに向かう。
memo
代理コードでは、元にあたるコードには進めない感じ。その他進行に向かない、微妙になる進行は2つ前後のコードに向かうもの等が該当する。
(特にSD機能同士とD機能同士がそうなる)
POINT
3つ先のコードになら無難に進む。基本的にドミナント以外のコードは1つ前後のコードに進める。(※VIIはD代理ゆえIに進める) TとT代理は自由が効くが、代理類にも傾向がある(と思われる)。IIIはDに近いTで、VIはSDに近いT。
例.メジャー系の進行先
- I…T「どこへでも」
- II…SD代理「IVには進めない。IやVII、VIも微妙。無難はD。IIIにもいける。」
- III…T代理(D寄り)「Iには進めないがVIには進める。IIやIVには行けるがVは×」
- IV…SD「Iやその代理(VIは微妙)、Vに進める。IIは微妙。VIIは行ける。」
- V…D「無難はTやその代理コードへの進行。」
- VI…T代理(SD寄り)「Iには進めない。」
- VII…DかSD?「Iに進める」
4.コードの選択肢を広げる考え方
コード進行にはダイアトニックから組むのが主ですが、「同主調や平行調※」またはドリアンスケールなどの他スケールをダイアトニック化したものからの借用も可能。
詩堂アタル
スケールの異なるダイアトニックから借りるとテンションの幅も代理コード(※※)の幅も広がる。
※メジャーダイアトニックから見れば同主調や平行調にはマイナー3種「ナチュラル-ハーモニック-メロディック」が使える。
※※コード内に含まれる音程が2つ以上共通してる場合 代用できるとされるコード。
これらの広がった選択肢は上記「3.」支配関係に当てはめて使うことが出来ます。
その他のバリエーション。dim化と裏コード等。
dimコードは構成音の関係で4種類しかないという話があります。そして それらはそれぞれドミナント7thに代用することが可能。- Cdim = E♭dim = G♭dim = Adim「B7, D7, F7, G#7」
- D♭dim = Edim = Gdim = B♭dim「C7, D#7, F#7, A7」
- Ddim = Fdim = A♭dim = Bdim「C#7, E7, G7, A#7」
ちなみに、G7からのA♭dimは並べ替えるとDdimになり、ドミナント変換でC#7(D♭7とも)というキーCの裏コードになる。
もっと他のバリエーション?異名類似音。
たとえばC7(♭13)というコードはCaugと解釈することも可能だったりします。上記のdimのドミナントセブンス化のような。他にもC6は並べ替えるとAmに出来たり。 名前が変わることで そこから続けるコードの解釈が変わり、進行先の選択肢を変えられる感じ。 AmとC6の例で考えるなら、これを使うことでCからのAmへの進行をCからのC6でペダル(ベースを同じにする進行方法の一) に出来る感じ。選択。コードにテンションノートを使う時
コードを場面、背景と解釈した場合、メロディはアクターといったところかと。メロディに使う場合は語りの感情のようになり、コードに使う場合は雰囲気を作るイメージ。 「長く聴かせたい場合はコード、流させたい場合はメロディ」など。 メロディで使ってるけどコード側にも雰囲気として欲しいってときとか、メロディには無いけど…ってときにも。memo
メジャー系のコードにはメジャー系マイナー系 両方のスケールを使え、マイナー系コードにはメジャー系スケールが使える感じ。
それらからメロディと合わせつつコード側も使用テンションのバリエーションを広げていける感じ。
音の重ね方。和音上は装飾。下は土台。
【和音 上】
音程効果が分かりやすい。和音の装飾部。7thや他、テンションノート類…都合が良ければメジャー、マイナーを分ける3rdも入ってくる域。
「目立たせたい音を置くための域」
【和音 下】
主にルートが一番下に置かれ、他は音の性質(テンションや音色等)の都合で上に置けなくなったトーン(5度とか)が ここに。
つまり、コードの中心部にあたる。「曲の芯を任されてる域」
ボイシング (クローズド、オープン)
- クローズド…密度がありパワーが出る。硬さや、濁りも得られる。
- オープン…音と音の間にスペースがあるため、広がりが出る。
まとめ &「理論とはルールなのか?」
- コード進行には「コードも歌う」「メロディに任せる」の2タイプが有
- メロディ作りの要領でルートラインから作ってみる方法
- ダイアトニックコードの関係を確認
- コードの選択肢を広げる考え方
こんな記事もあります
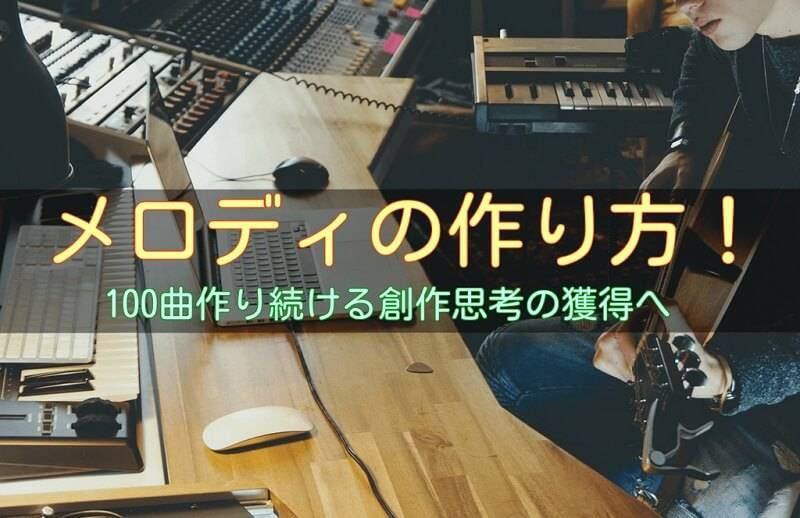
「作れない」卒業!メロディの作り方のたった2つのコツ
...

作編曲(アレンジ)のコツが掴めないDTMerに思考整理テクニック
...
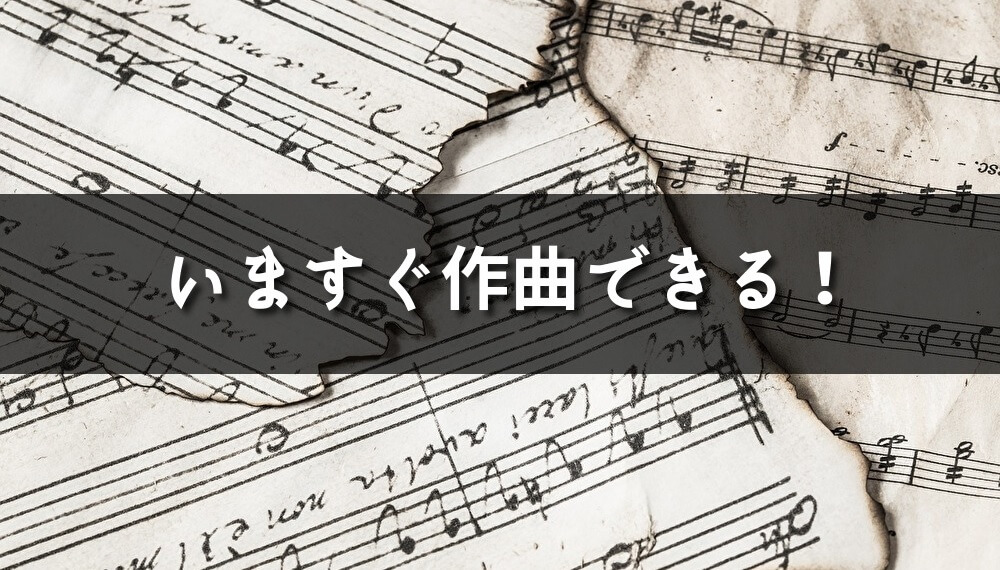
作曲したい初心者さんに「簡単に曲が作れるようになる」話
...

